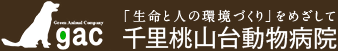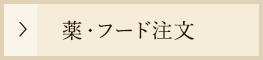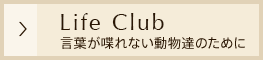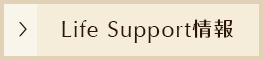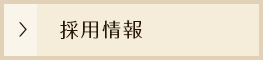ライフサポート情報
2025.04.23|ライフサポート情報
吠える、毛を噛む…|それ、環境ストレスが原因かもしれません
愛犬や愛猫が突然吠えるようになったり、自分の毛を噛んでしまったりすることはありませんか? こうした行動の背景には、環境ストレスが隠れている可能性があります。犬や猫は私たちが思いもしない些細な変化にも敏感に反応し、ストレスが積み重なると体調や性格、行動などに悪影響を及ぼすことがあります。
ストレスを放置すると、嘔吐や下痢といった消化器症状が現れることがあり、ひどい場合には膵炎につながるケースもあるため注意が必要です。
今回は、犬や猫の環境ストレスの要因やサイン、改善方法などについて詳しく解説します。
■目次
1.環境ストレスとその影響
2.早期発見のためのストレスサイン
3.予防と改善のための環境づくり
4.よくある質問(Q&A)
5.まとめ
環境ストレスとその影響
犬や猫がストレスを感じる原因はさまざまですが、特に以下のような環境要因が関係していることが多いです。
<生活音>
テレビの音や掃除機の音、工事の騒音など、大きな音がストレスとなることがあります。特に繊細な性格の子は、足音やドアの開閉音などの些細な音にもストレスを感じることがあります。
<照明>
お留守番をさせるとき、帰りが遅くなる場合は照明をつけて出かける飼い主様は多いですが、犬や猫にとってはこれがストレスになることがあります。本来、犬や猫は自然の光の変化に適応して生活しており、長時間の人工的な明かりが体内時計を乱す原因になるためです。特に、深夜まで明るい環境が続くと睡眠の質が低下し、ストレスが蓄積してしまいます。
<温度>
犬は20℃前後、猫は25℃前後が適温とされています。これを大きく上回ったり下回ったりするとストレスの原因となるため、適温を保つことが重要です。また、急激な温度変化も負担となるため、エアコンや暖房をうまく調整しながら管理しましょう。
<空間の使い方>
人通りが多い場所やテレビの近くに寝床を設置すると、犬や猫が落ち着いて休むことができません。そのため、落ち着ける専用スペースを確保することが重要です。
<多頭飼育の場合>
新しく犬や猫を迎え入れる際、先住の子との相性が悪かったり、飼い主様の愛情が分散されたりすることで、ストレスが生じることがあります。特に猫は縄張り意識が強いため、新しい猫が来ることで大きなストレスを感じることがあります。
<家族構成の変化>
赤ちゃんが生まれる、家族の誰かが引っ越す、仕事の都合で留守が増えるといった変化も、犬や猫にとってはストレスの要因になります。これまでの生活習慣が変わることで、不安や寂しさを感じることがあるため、注意が必要です。
<飼い主様の生活習慣の変化>
仕事の都合で帰宅時間が遅くなる、散歩や食事の時間が変わるといった変化も、犬や猫のストレスにつながります。特に、突然の変化は犬や猫にとって大きな負担になるため、少しずつ適応できるように工夫することが大切です。
犬や猫はストレスを感じると嘔吐や下痢といった消化器症状が現れることが多く、場合によっては膵炎に繋がるケースもあるため、注意が必要です。
早期発見のためのストレスサイン
ストレスを早期に発見するためには、日頃の行動の変化に気を配ることが大切です。以下のような兆候が見られる場合、ストレスが溜まっている可能性があります。
<初期のサイン(軽度)>
・あくびをする
・尻尾を下げる
・耳を倒す
・体を頻繁に掻く
・毛を噛み、部分的に短くなる(特に猫に見られる)
<中程度のサイン>
・突然に攻撃的になる(唸る、噛む、暴れる)
・震える
・鳴き続ける
・呼吸が荒くなる
・寂しさからいたずらをする(誤食のリスクも)
<重度のサイン>
・下痢や嘔吐が続く
・食欲不振
・元気がなくなる
・自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回る
・手足の同じ場所を舐め続けて炎症が起こる
・粗相をする
・瞳孔が開いたままになる(猫)
・ペットシーツを破り、飲み込んでしまう
これらの異常にいち早く気がつくためには、日頃から犬や猫の食事や排泄、睡眠の様子を観察し、小さな変化も見逃さないようにしましょう。
予防と改善のための環境づくり
ストレスを改善するためには、以下のように生活環境を変えることが大切です。
<快適な休息スペースを確保する>
犬や猫が静かに安心して過ごせる休息スペースを確保しましょう。人通りが少なく、騒音が少ない場所が理想です。基本的に犬も猫も暗く静かな場所を好みますが、寂しがり屋の子の場合は飼い主様の姿が見える範囲で寝床を用意するとよいでしょう。
<照明で生活リズムを整える>
深夜まで明るいと体内時計が乱れるため、過度な照明は避けましょう。間接照明やデスクライトを活用することで、適度な明るさを保つことができます。
<温度管理を徹底する>
一年を通して適温を維持し、急激な温度変化を防ぎましょう。エアコンやヒーターを使いながら、温度が一定になるように調整してください。
<適度な運動とコミュニケーションを取る>
ストレス発散には、運動や遊びが効果的です。散歩やおもちゃ遊びを取り入れ、飼い主様とのコミュニケーションの時間を増やしましょう。
<サプリメントの活用>
犬や猫の不安を和らげるようなサプリメントを使う方法も有効です。ただし、サプリメントを活用する場合は、獣医師に相談しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q:手や足をずっと噛んでいるのですが、ストレスが原因ですか?
A:皮膚に異常がなければ、ストレスが原因の可能性があります。暇つぶしの場合もあるため、遊びや運動、コミュニケーションの時間を増やし、改善しない場合は動物病院を受診しましょう。
Q:インターホンが鳴るとずっと吠えているのですが、ストレスに繋がっていますか?
A:場合によってはストレスに繋がることがあります。というのも、「お客さんがきて嬉しい」もしくは「見知らぬ人がテリトリーに侵入しようとしている」という両極端な理由から、犬はインターホンの音に対して吠えるからです。
前者の場合はストレスに繋がることはありませんが、後者の場合は大きなストレスに繋がってしまいます。そのため、しつけによって「インターホンが鳴ったら良いことが起こる」ということを愛犬に教えることで、ストレスを解消することができます。
当院ではパピー教室を開催しておりますので、なかなか状況が改善しない場合やしつけ方がよくわからないという方は、ぜひお気軽にご参加ください。
Q:ストレスが原因と診断されましたが、どれがストレスか全くわかりません。
A:ストレスの原因は多岐にわたるため、生活環境を見直してみましょう。改善策が見つからない場合は、獣医師に相談することをおすすめします。
まとめ
犬や猫は環境の変化に敏感で、ストレスを溜めることで体調不良や病気のリスクが高まります。そのため、生活環境を整え、適度な運動やコミュニケーションを取りながら、ストレスの少ない暮らしを心がけましょう。
もし、愛犬や愛猫のストレスが疑われる場合や症状が改善しない場合は、お気軽に当院までご相談ください。
年中無休で動物たちの健康をサポートします
千里桃山台動物病院
TEL:06-6190-5100