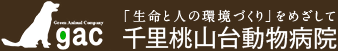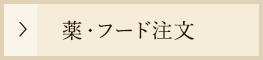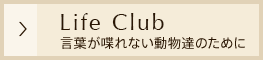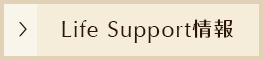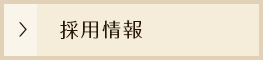ライフサポート情報
2025.10.24|ライフサポート情報
犬や猫の足舐め行動に要注意|アレルギーや皮膚病の可能性とは?
愛犬や愛猫が「また足を舐めている」「ずっと同じところを噛んでいる」といった行動を見かけた際に、「ただの癖では?」と思ってしまったことはありませんか? このような行動は、単なる癖ではなく皮膚病やアレルギー、ストレスといった体や心の異変のサインかもしれません。
こうした症状を放置すると、皮膚の状態が悪化したり、慢性疾患に繋がってしまったりすることもあるため、早期の受診と適切な治療を行うことが大切です。
今回は、犬や猫が足を舐めたり噛んだりする理由について、原因や症状、治療方法などをご紹介します。
■目次
1.犬や猫が足を舐める・噛む行動とは?
2.原因
3.心理的・環境的な要因
4.飼い主様が気づくべきサインとは?
5.診断方法
6.治療方法
7.ご家庭でできるケアと予防法
8.まとめ
犬や猫が足を舐める・噛む行動とは?
犬や猫は日常的に自分の体を舐めたり毛づくろいをしたりすることで、清潔を保つ習性があります。これは「グルーミング」と呼ばれる自然な行動で、健康な犬や猫であれば誰でも行っています。
しかし、足だけを集中して頻繁に舐め続けたり、噛むような仕草を繰り返したりするようであれば注意が必要です。特に、毛が抜ける、皮膚が赤くなっている、傷ついているといった症状が見られる場合は、明らかに正常なグルーミングとは異なります。
また、シニア期の犬や猫でこのような行動が急に始まった場合は、身体に異常があるサインである可能性が高く、早急な診察が求められます。
原因
犬や猫が足を舐めたり噛んだりする背景には、さまざまな身体的なトラブルが隠れている可能性があります。特に以下のような疾患が関与しているケースが多く見られます。
・皮膚病(アトピー性皮膚炎、細菌感染、真菌感染、犬の指間炎など)
・アレルギー(食物アレルギーや環境アレルギーなど)
・外傷(擦り傷や切り傷など)
・異物(肉球や指の間に小石や草の種などが挟まっている場合)
・関節や神経の異常(痛みや違和感が足に集中して現れるケース)
これらの疾患は早期に対処することで重症化を防ぐことができます。特に犬の指間炎のように、足先の炎症が慢性化しやすい病気は、放置してしまうと日常生活に大きな支障をきたすこともあるため、注意が必要です。
心理的・環境的な要因
足舐めや足を噛む行動は、身体の病気だけが原因ではありません。以下のように犬や猫の心の状態や、生活環境に起因するケースも少なくありません。
<ストレス>
環境の変化(引っ越し、家族構成の変化など)や、騒音、過度な留守番などがストレスとなり、それを紛らわすために過剰なグルーミング行動をすることがあります。
犬や猫の環境ストレスの要因や改善方法についてより詳しく知りたい方はこちら
<退屈>
刺激の少ない単調な生活を送っていると、退屈しのぎに足を舐めたり噛んだりしてしまう場合があります。特に運動不足や遊びの時間が足りていない犬や猫に見られます。
<分離不安>
飼い主様と離れることへの不安が強く、「分離不安症」と呼ばれる行動障害につながることがあります。この場合、飼い主様の姿が見えなくなっただけで強い不安を感じ、その不安を紛らわせるために足や尻尾をしつこく舐めたり噛んだりします。
なお、心理的な要因によって足舐め行動が始まり、そこに皮膚病などの身体的疾患が併発するというように、複数の原因が重なっているケースも多くあります。そのため、原因を一つに絞らず、総合的な診断が重要になります。
飼い主様が気づくべきサインとは?
以下のような症状が見られる場合には、足舐めや噛み行動が単なる癖ではなく、明らかな異常のサインである可能性が考えられます。
・舐めたり噛んだりする頻度が明らかに多い
・同じ場所ばかりを繰り返し舐める
・足の皮膚に赤み、脱毛、膿、ただれなどが見られる
犬の皮膚トラブルの原因や自宅でできるケアについてより詳しく知りたい方はこちら
これらの症状が見られた場合、自己判断で様子を見るのではなく、速やかに動物病院を受診することが大切です。
また、初期に目立った異常がない場合でも、時間の経過とともに状態が悪化するリスクがあります。悪化してからでは治療期間が長引き、皮膚が完全には元通りにならない可能性もあるため、早期の対応が重要です。
診断方法
足舐めや足噛みの行動が見られた場合、まずは「癖」なのか「病気のサイン」なのかを明確に区別する必要があります。
当院では、以下のようなステップで診断と治療を進めています。
①問診・視診:生活環境や行動パターンを確認します。
②皮膚検査:細菌や真菌の感染有無を確認します。
③血液検査:アレルギーや内臓疾患の可能性を調べます。
④アレルゲン検査:特定の食材や環境因子に対する反応を確認します。
⑤画像診断(CT・MRI):関節や神経の異常が疑われる場合に実施します。
診断で原因が判明したあとは、症状や体質に応じて治療方針を決定します。
治療方法
治療には、以下のような方法を組み合わせて行います。
・外用薬や内服薬の投与
・食事療法(アレルギー除去食や栄養補助)
・生活環境の見直し(ストレス要因の排除)
・定期的な皮膚ケアと再診による経過観察
このように当院では、単一の治療だけでなく、犬や猫の生活全体を見据えた総合的なアプローチを大切にしています。
なにか分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
ご家庭でできるケアと予防法
犬や猫の足舐めが気になるとき、以下のような工夫を行うことが大切です。
<清潔な環境を保つ>
爪や肉球にケガや異物がないかを確認し、散歩のあとは足を洗って清潔を保ちましょう。また、寝具やクッションなどもこまめに洗濯し、衛生的な環境を整えることが基本です。
<ストレスをためない>
頭を使うおもちゃや知育遊びで刺激を与えたり、ドッグランやキャットタワーなどで自由に体を動かす時間をつくったりすることも有効です。
すぐに実践できる犬や猫との室内での遊び方についてより詳しく知りたい方はこちら
このように、適度な運動と休息をバランスよく取り入れた生活を送ることで、心身の健康を保ちやすくなります。
ただし、飼い主様による自己判断で足舐め行動を無理にやめさせようとすると、犬や猫のストレスを悪化させ、症状が進行してしまう危険性があります。特に、身体的な疾患が隠れている場合は、専門的な治療が必要になるため、気になる様子がある場合は必ず動物病院で原因の特定を行ってください。
まとめ
足を舐めたり噛んだりする行動は、犬や猫の心や体に何らかの不調が起きている可能性が考えられます。見た目には単なる「癖」に見えるかもしれませんが、その裏には皮膚病やアレルギー、ストレスなど、見過ごせない異常が隠れていることがあります。
飼い主様が早期に異変に気づき、適切なタイミングで動物病院を受診することで、重症化を防ぎ、愛犬や愛猫の快適な生活を守ることができます。
当院では、先端医療機器と低侵襲治療を取り入れた診療を行い、清潔で安心できる環境の中で、飼い主様と犬や猫の両方に寄り添った医療を提供しています。犬や猫の足舐め行動や皮膚の異変にお悩みの際は、ぜひ一度当院にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
夏に急増する!?|愛犬や愛猫の皮膚トラブルについて
年中無休で動物たちの健康をサポートします
千里桃山台動物病院
TEL:06-6190-5100