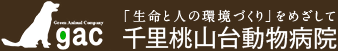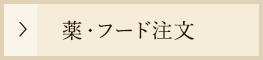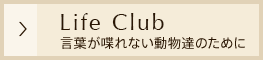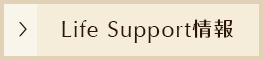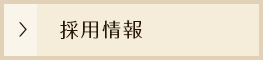ライフサポート情報
2025.09.10|ライフサポート情報
口臭になる前に!愛犬・愛猫の口臭を防ぐ生活習慣と予防のコツ
愛犬や愛猫に顔を近づけたとき、「なんだか口が臭うかも…」と感じたことはありませんか?その一方で、「毎日元気に過ごしているし大丈夫そう」と見過ごしてしまっている飼い主様も少なくありません。
口臭はお口のトラブルだけでなく体全体の健康とも関わっているため、日頃からの予防が大切です。毎日のちょっとした習慣を見直すことで、愛犬や愛猫の健康を守ることにつながります。
今回は、犬や猫の口臭の予防方法を、獣医師の視点から詳しくご紹介します。
■目次
1.食事で変わる!口臭予防につながる食生活のポイント
2.環境づくりが口臭予防のカギ!ストレス軽減と生活リズムの整え方
3.年齢別の口臭予防アプローチ
4.Q&A(よくある質問)
5.まとめ
食事で変わる!口臭予防につながる食生活のポイント
食生活は口腔内の環境に大きな影響を与えます。口臭予防につながる食事管理のポイントは以下の通りです。
<食事のタイミングと回数>
1日を通してフードを置きっぱなしにする「置き餌」は、口臭の原因になることがあります。フードは長く放置すると酸化しやすく、口の中の環境にも悪影響を及ぼすため、フードは1日2〜3回を目安にしっかりと時間を決めて与えましょう。食べ残しは放置せず、20〜30分ほどで片づけてください。
<フードの選び方>
ウェットフードは歯に食べかすが残りやすく、歯垢や歯石の原因となりやすいです。そのため、特別な栄養管理が必要な場合を除き、なるべくドライフードを中心に与えると良いでしょう。また、ドライフードは歯の表面を適度にこすってくれるため、物理的な歯垢除去の効果も期待できます。
<食後の口腔内ケアのタイミング>
歯垢は食後から8時間程で形成され、2〜3日放置すると歯石へと変化してしまいます。歯石は歯周病の大きな原因となり、強い口臭を引き起こします。歯周病を未然に防ぐためにも、歯磨きは1日に1回、難しい場合は2〜3日に1回は行うようにしましょう。
犬と猫の口腔ケアの重要性やケアをする際の注意点についてより詳しく知りたい方はこちら
<水分摂取を促す>
口の中が乾燥すると唾液の働きが低下し、細菌が繁殖しやすい状態になります。特に夏場は脱水によって口の中が乾きやすくなるため、新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげることが大切です。
環境づくりが口臭予防のカギ!ストレス軽減と生活リズムの整え方
口臭の予防には食事だけでなく、以下のような環境の整備も大切です。
<ストレスを減らす>
犬や猫が強いストレスを受けると唾液の分泌が減り、口の中が乾きやすくなります。その結果、口臭が強まったり、口腔内の免疫力が下がって口内炎が起きたりする場合もあります。そのため、犬や猫ができるだけ安心して過ごせる環境を整えてあげることが大切です。
<適度な運動を取り入れる>
運動不足は代謝の低下を招き、体内の老廃物が原因で口臭が発生することがあります。そのため、毎日の散歩や遊びを取り入れることが大切です。ただし、夏場の激しい運動は体温上昇による開口呼吸を引き起こし、口内乾燥から口臭を悪化させる場合があるため、涼しい時間帯を選んで無理のない範囲で運動を行いましょう。
<食器や給水器を清潔に保つ>
食器や給水器が不衛生な状態のままだと、唾液に含まれる細菌が繁殖し、その雑菌を再度体内に取り込んでしまうことになります。そのため、食器は毎食後に洗い、給水器は毎日水を交換し、最低でも週1回はしっかり洗浄するように心がけましょう。
年齢別の口臭予防アプローチ
犬や猫の口臭対策は、以下のようにライフステージごとに適したケアを取り入れることで、より効果的な予防が可能になります。
<子犬・子猫の場合>
生後3週間ごろから乳歯が生え始め、歯磨きのトレーニングを開始できるようになります。新しい環境に慣れてきたら、少しずつ口元に触れる練習を始め、将来のスムーズなデンタルケアに備えていきましょう。
子犬・子猫の歯磨きトレーニングについてより詳しく知りたい方はこちら
<成犬・成猫の場合>
犬や猫は3歳を過ぎると、約8割が歯周病を抱えているといわれています。歯磨きを中心とした日々のケアに加え、少なくとも半年に1回の歯科検診、さらに1〜2年に1回はスケーリング(歯石除去)を受けることが推奨されます。
犬と猫の口臭と歯石除去(スケーリング)についてより詳しく知りたい方はこちら
<シニア期の犬や猫の場合>
年齢を重ねると、運動量や代謝が低下し、生活リズムの乱れや免疫機能の低下が目立ち始めます。これにより、口腔内トラブルも発生しやすくなるため、3か月に1回程度の歯科検診に加え、より丁寧な日常ケアが必要です。
また、腎臓病や肝臓病など、内臓疾患が原因で口臭が強くなるケースもあります。こうした病気の早期発見のためにも、半年に1回の定期健康診断を受けておくと安心です。
Q&A(よくある質問)
Q:口臭予防はいつから始めるのが効果的ですか?
A:歯が生え始める生後3週間ごろから、口元に触れる練習をスタートするのが理想的です。
Q:忙しくても続けられる口臭の予防方法はありますか?
A:デンタルトイや、飲み水に混ぜるだけのデンタルケア用品の使用がおすすめです。ほかにも様々なケアアイテムがありますので、お困りの際は当院にご相談ください。
Q:口臭予防の効果はどのくらいで実感できますか?
A:効果の実感には個体差があります。もともとの口腔内環境やケアの頻度によって異なるため、無理なく続けることが大切です。
まとめ
犬や猫の口臭は、ただの「においの問題」ではなく、健康を映し出すサインでもあります。そのため、口臭が気になり始めてから対処するのではなく、日頃からの食事や生活習慣の見直し、適切なケアによって未然に防ぐことが何よりも重要です。
また、子犬や子猫のうちから歯磨き習慣づけ、年齢に応じた検診やケアを取り入れることで、長く健康な生活を送ることができます。
もしすでに口臭が気になる場合や、どのようにケアを始めたらよいか分からない場合には、早めに動物病院で歯科検診を受けることをおすすめします。
当院では、犬や猫の口臭予防に関するご相談や、適切なデンタルケアのご提案を行っております。気になる症状がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
犬と猫の口腔ケアの重要性|健康的な歯と歯茎のための対策法とは?
犬と猫のための歯科をお探しの方へ|愛犬や愛猫の健康を守る動物病院
年中無休で動物たちの健康をサポートします
千里桃山台動物病院
TEL:06-6190-5100