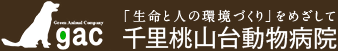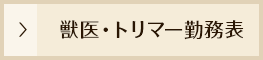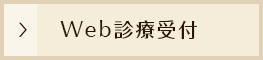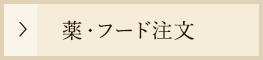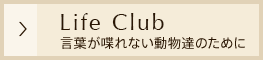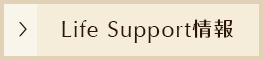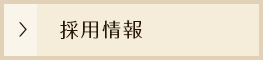ライフサポート情報
2025.02.17|ライフサポート情報
愛犬や愛猫の水を飲む量が以前よりも増えた or 減った?|適切な飲水量と大切なサイン
愛犬や愛猫が水を飲む量が増えたり減ったりしていると感じたことはありませんか?実は、水を飲む量は健康状態を知るための重要なバロメーターのひとつです。そのため、適切な飲水量を把握することで、愛犬や愛猫の健康を守り、病気の早期発見につながります。飲水量の変化は生活環境や食事の影響だけでなく、病気のサインである場合もあります。
今回は犬や猫の適切な飲水量の目安や、その変化が示す可能性のある病気、そして適切な対処法などについて詳しく解説します。
■目次
1.愛犬や愛猫の適切な飲水量とは?
2.飲水量が増える原因と考えられる病気
3.飲水量が減る原因と考えられる病気
4.飲水量の変化に気づいたら
5.まとめ
愛犬や愛猫の適切な飲水量とは?
犬や猫の適切な飲水量を知ることは、健康管理において非常に重要です。一般的な目安として、犬の場合は体重1kgあたり1日に約50mL、猫の場合は体重1kgあたり約60mLの水を飲むとされています。例えば、3kgの犬であれば約150mL、5kgの猫であれば約300mLが目安となります。
ただし、この飲水量はあくまで目安であり、以下のような要因によって変動することがあります。
<季節の影響>
夏場や運動後など気温が高い時期は飲水量が増える一方で、冬場は飲水量が減少しやすくなります。
<食事の種類>
ドライフードを主食にしている場合は、水分摂取量を補うために飲水量が多くなる傾向があります。一方で、ウェットフードを与えている場合は、食事から水分を摂取できるため、飲水量が少なくなることがあります。
<運動量>
活発に運動した日は、体内で消費された水分を補うために飲水量が増加します。
飲水量を確認する簡単な方法として、24時間の間に与えた水の量と残った水の量を比較する方法があります。また、決まった時間に新しい水を入れ直すことで、正確な飲水量を把握することも可能です。それにより、日頃から飲水量をチェックしておくことで、異常に気づきやすくなります。
飲水量が増える原因と考えられる病気
愛犬や愛猫がいつもより多く水を飲んでいる場合、それは単なる喉の渇きではなく、以下のような病気のサインである可能性があります。
<腎臓病>
腎臓の機能が低下すると、体内で水分を効率よく再吸収する能力が弱くなり、多飲多尿といった症状が現れます。腎臓病は特に高齢の犬や猫に多い病気で、早期発見が重要です。
<糖尿病>
血糖値が高い状態が続き、尿とともに大量の水分が失われるため、体が水分を補おうと多飲になります。他にも食欲増進や体重減少、疲れやすさなどが見られることがあります。
<クッシング症候群>
クッシング症候群とは、副腎が過剰にホルモンを分泌する病気で、多飲多尿のほか、皮膚が薄くなる、毛が抜ける、お腹が膨らむといった症状が現れることがあります。
特に高齢の犬や猫では、これらの疾患が発症しやすくなります。飲水量が増えるだけでなく、食欲や体重、尿の量や回数にも変化が見られる場合は、早めに動物病院で診察を受けましょう。
飲水量が減る原因と考えられる病気
逆に、飲水量が減る場合も注意が必要です。飲水量の減少には、以下のような原因が考えられます。
<消化器系の病気>
食欲不振や嘔吐などが伴う場合、胃腸のトラブルが原因で飲水量が減少している可能性があります。この場合、無理に水を飲ませると逆効果になることもあるため、注意が必要です。
<口腔内の痛み>
歯周病や口内炎があると、水を飲む際に痛みを感じるため、飲水を避けるようになります。特に猫では重度の口内炎がよく見られ、犬では歯石の付着による歯周病が多いです。定期的な歯磨きや歯科ケアが重要です。
犬と猫の口臭と歯石除去(スケーリング)についてはこちらから
犬と猫のための歯科治療についてはこちらから
犬と猫の口腔ケアの重要性についてはこちらから
<冬場の影響>
気温が低くなる冬場は喉の渇きを感じにくくなるため、飲水量が減ることがあります。しかし、水分不足により尿結石や脱水症状が起きやすくなるため、複数の水飲み場を用意したり、犬や猫用のスープやミルクを与えて水分摂取量を増やしたりする工夫が必要です。
<脱水症状の危険性>
飲水量が減少すると、脱水症状が起こる可能性があります。脱水の初期症状として、元気がない、食欲の低下、下痢や嘔吐、尿の減少や濃い色の尿、皮膚の弾力低下などが挙げられます。皮膚をつまんだ際に戻るのが遅い場合や、歯茎が乾燥している場合は重度の脱水が疑われます。これらの症状が見られた場合は、早急に動物病院を受診しましょう。
飲水量の変化に気づいたら
飲水量の変化に気づくことは、犬や猫の健康管理において非常に重要です。普段から飲水量をチェックし、以下のポイントを把握しておくことで、早期発見につながります。
<普段の飲水量を知る>
健康な時の飲水量を定期的に測り、記録しておくことが大切です。
<変化に気づいたら記録する>
飲水量が増えた、または減った場合には、いつからどのように変化したのかをメモしておきましょう。それにより、動物病院での診察時に役立ちます。
<他の情報も記録する>
飲水量の変化とともに、食事量や排尿回数、嘔吐や下痢などの症状も記録しておくと、より正確な診断につながります。
動物病院を受診する際には、こうした記録が獣医師にとって重要な情報となります。
まとめ
犬や猫の飲水量は健康状態を知る重要な指標であり、適切な飲水量を把握することで、病気の早期発見と予防につながります。飲水量が増えたり減ったりする場合には、それが一時的なものであっても注意深く観察し、必要に応じて動物病院を受診してください。
飼い主様の日々の観察が、愛犬や愛猫の健康を守る大きな力になります。そのため、普段から飲水量をチェックし、些細な変化にも気づけるように心がけましょう。
年中無休で動物たちの健康をサポートします
千里桃山台動物病院
TEL:06-6190-5100